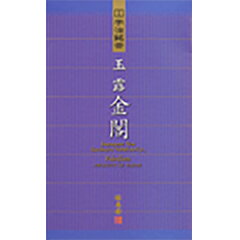京都府木津川市の上狛環濠と茶問屋街の町並みで、ブログ用の写真を撮り忘れた場所があったので、後日再訪すると前回訪問時に閉まっていた福寿園資料館が「開館」していました。
HPには「事前予約が必要」との旨が書いてあったのですが、次来る機会がいつになるかかもわからなかったので、思い切って飛び込むと見学可能とのこと。
迷わず入館することにしました。
受付に館員さんがおられる場合は、予約なしでも利用できるとのことですが、会議などで席を外されている場合もあるそうで、確実に入館したい場合は、事前に電話で予約するのがおすすめです。
資料館は、下図のように3つのゾーンに分かれています。

資料館の別館1、2は本店向かいの町屋を買い取って改修された建物とのこと。
茶店
受付のある茶店は、旧奈良街道から茶問屋ストリートを東に入ってすぐの場所にあります。

受付で入館料の500円を支払います。

まずは御座敷に通していただき、ここでお茶をいただきます。

ここで用意していただけるお茶は、高級玉露。100gで5000円程するかなり高価なお茶で、ほとんどの人はめったに口にすることのないお茶かと思います。

まず1杯目は、玉露独特の風味を味わえる、以下のお作法でいただきます。
①90℃のお湯を、茶碗に6分目ほどの量を注ぎ、「湯冷まし」に移した後、40℃くらいまで冷ます。
※手で持ってほんのり温かい程度が目安。
②茶葉を入れた急須にお湯を注ぎ、3分待つ。
※時間は砂時計で測ります。
③茶碗へお茶を注ぐ。
※この時、しっかりと茶葉からお湯を1滴残らず切るように注ぐと旨味がより抽出されます。
館員さんの丁寧な説明にしたがって、無事に抽出完了!

ゆっくりと舌の上で転がすようにお茶を口に含むと、お出汁のような濃厚な旨味が、じわっと広がります。

ちょっとお茶としては味わったことのない、高級カツオのお出汁にも似た独特の旨味で、大変美味しいです。
玉露はそもそも旨味成分が多く、低温で抽出することで、より旨味が増すのだとか。
これはぜひ、たくさんの方に味わっていただきたい味です!
2杯目以降は、普通に熱いお湯を注いでいただきますが、こちらも大変甘みがあって美味しいお茶。
同じ茶葉のはずなのに、全然味が違うのが驚きです。
お湯の温度や淹れ方で、ここまで味が変わるか!?と貴重な体験をさせてもらいました。
あと、お茶を淹れまで時間があったので、館員さんと色々お話しできたのも楽しかったです。
福寿園さんといえば、サントリーの緑茶飲料「伊右衛門」のイメージが強いですよね。
「伊右衛門」以前にも、福寿園さんのほうでは缶の茶飲料を製造されていたとのことで、こちらの売れ行きがイマイチだったこともあり、「伊右衛門」を販売開始した際は、社内でも本当に売れるだろうかと懐疑的な空気もあったそうです。
また、商品名もサントリー側から福寿園初代当主「福井伊右衛門」の名前を使いたいと提案されたそうですが、ちょうど発売された2004(平成16)年、東海道四谷怪談を題材とした「嗤う伊右衛門」が公開されたこともあり、お岩を貶める悪役の伊右衛門と同名で「イメージが悪いのでは」という声もあったとか。
売れ行きへの不安もあったのか、最初は非常に生産数を抑えて出荷されたそうですが、わずか1週間で売り切れてしまうほどのヒット商品になり、現在ではペットボトル茶飲料のトップブランドに成長しました。
あと、産地表示についても、伝統的に京都、奈良、伊賀、滋賀産の茶葉を京都の茶匠がブレンドしたものを「宇治茶」として扱ってきましたが、静岡などから「京都産でもないものを宇治茶というのは産地表示がおかしい」などと指摘されてしまうのに困惑されていました。
筆者個人としては、産地の特性に合わせて、経験豊かな茶匠が産地の違う茶葉をブレンドして味を調えることに値打ちがあり、「宇治茶」は単なる「京都産茶葉」そのもののブランドというより、「京都の茶匠がブレンドした茶葉」というところに本当のブランドがあり、極論を言えば、京都産の茶葉が一つも使われていなくても、成立するものとさえ思っています。
どうも、ワインとブレンドウィスキーを同列に扱うような議論で、結局消費者の利益にはつながらない不毛な議論に感じるのは筆者だけでしょうか。
茶問屋
お茶を5杯ほどいただき、資料館別館2へ移動します。

庭を通って移動します。

江戸時代~昭和初期の茶問屋の店先を再現した展示になっています。

かつては茶問屋の店先で、試飲などさせてもらえたのかな。

茶葉の品質を確認する当時の道具が展示されています。

資料館本館
資料館本館は製茶所の展示になっています。

「蒸し」や「手もみ」など、製茶の工程について、手作業の時代の道具から近代機械化された後の機材が展示されていました。

こちらは蒸し器と揉機。


日本製で、昭和初期くらいの機械です。
農協の共同作業場で使われていたとのこと。
こちらは最終段階で、茶葉の選別を行っていた台と箱です。

製茶された商品は、冷蔵庫がない時代は出荷されるまで、地下貯蔵庫に保管されていました。

こちらは「ほいろ」という手もみ製茶の道具です。

茶畑で使う昔の茶摘み道具も展示されていました。

ちなみに京都や奈良、滋賀、三重(伊賀)の関西のお茶が山間部の斜面で栽培されるのに対して、九州、特に鹿児島のお茶は、平野部の大規模な茶畑で栽培するため、収穫の機械化が容易で人件費をかなり低く抑えられ、比較的安価になるそうです。
資料館前の建物は、もともと福寿園のオーナー家の住宅だったそうです。

現在、茶問屋街ストリートにはスイーツや喫茶を楽しめるスペースはないのですが、そういったスペースを設ける構想はあるとのこと。
上狛地区は現状観光地化されていないこともあり、国道沿いのコンビニくらいしか休憩スペースがありません。
カフェやお土産を買えるスポットが茶問屋街ストリートにできたら、周辺散策の拠点になるかと思います。
理想は伊勢のおかげまち・おかげ横丁のように、町全体が人の集まるスポットになれば最高ですね。
ただ、旧山城町が町村合併で木津川市になってから、「お茶の町」というPRは少し弱くなってきている印象を受けます。
茶問屋街のある上狛は、奈良街道と伊賀街道の辻と、伊賀から大阪湾へ通じる木津川水運の川湊が近接する古くからの交通の要衝で、幕末から明治にかけ最盛期には120軒もの茶商が軒を並べた歴史ある町。
現存する京都府最大の環濠集落・上狛(大里)環濠も茶問屋街から国道24号線を挟んで北に広がるなど、歴史的な景観も残り、JR上狛駅もあって交通アクセスも悪くありません。
現在もこの小さな地域で、実に20軒ものお茶業者が営業を続け、全国屈指のブランド力を持つ「京都のお茶」を下支えしている点でも、筆者のような他県人から見てると、スゴイ場所に見えます。。
もう一押し、二押し、散策の目玉ができれば、もっと注目されるんじゃないか、と大きなポテンシャルを感じさせる町であり、スポットでした。
〇基本情報
■電話:0774-66-6280
■住所:京都府木津川市山城町上狛東作り道16(福寿園本社西)
■開館時間:10時~12時、13時~16時
■休館日:不定休
■入館料:500円
■アクセス:JR奈良線「上狛駅」から徒歩約8分
■地図
玉露は今回生まれて初めて飲みましたが、いつも飲んでる煎茶とは全く味が違うのが驚きでした。